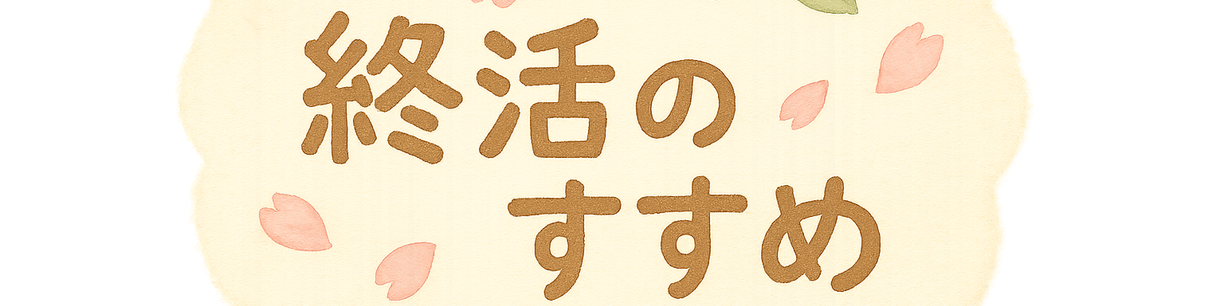終活のマニュアルを知りたい方へ終活するための8ステップの解説

昨今「終活」と言う言葉が定着してきました。この言葉が定着した背景には、これまで故人の希望や意向をわからないまま遺族が対応したり、遺族が初めての事でどうした流れで対処していけばよいかわからず、混乱を招いていたことによる不便さ解決のための糸口になったと考えます。最初こそ耳慣れないため、嫌悪感を感じている人もいましたが、今では年代を若くしても終活している方々も見受けます。実際に私自身もシングルマザーなので、いつなにがあっても子供に迷惑をかけたくないという思いから、終活はできる限りしてあります。故人にとっても自分の希望を伝えられる手段にもなり、遺族にとっても参考書となりうる終活は、決してマイナスではなく前向きな作業のように感じます。本記事では、「終活とはどんなのか」や「終活のマニュアル」を紹介しています。終活の流れをステップで解説していきますので今から始めたい方、興味がある方は最後まで一読いただけますと幸いです。 終活とは、「人生の終わりについて考え、残す活動」要するに、ご自身が亡くなった時の身の回りの生前整理、病気などで判断力を失った時のために医療・介護についての要望・希望などを残す作業です。終活で準備をおこなうことで、将来の不安が少なくなり、残りの人生を楽しく過ごせると同時に残していく人たちの負担を減らすこともできるのです。終活において大事なことは、自分の望む最期を迎えられるように、元気なうちから準備することなのです。きちんと要望を家族や周りの人に伝えられ、ポジティブに考えらえる時に活動することが大事。そして自分が過去残されたときに苦労したことや、困ったことを自分が残していきたくないという経験則からの気持ちも、形として現わせます。どこまで思い通りになるかは別としても、自分の要望を、参考にでも残しておくことが自分にとっても、遺される人にとってもプラスに働くでしょう。
終活とは、「人生の終わりについて考え、残す活動」要するに、ご自身が亡くなった時の身の回りの生前整理、病気などで判断力を失った時のために医療・介護についての要望・希望などを残す作業です。終活で準備をおこなうことで、将来の不安が少なくなり、残りの人生を楽しく過ごせると同時に残していく人たちの負担を減らすこともできるのです。終活において大事なことは、自分の望む最期を迎えられるように、元気なうちから準備することなのです。きちんと要望を家族や周りの人に伝えられ、ポジティブに考えらえる時に活動することが大事。そして自分が過去残されたときに苦労したことや、困ったことを自分が残していきたくないという経験則からの気持ちも、形として現わせます。どこまで思い通りになるかは別としても、自分の要望を、参考にでも残しておくことが自分にとっても、遺される人にとってもプラスに働くでしょう。


終活とは
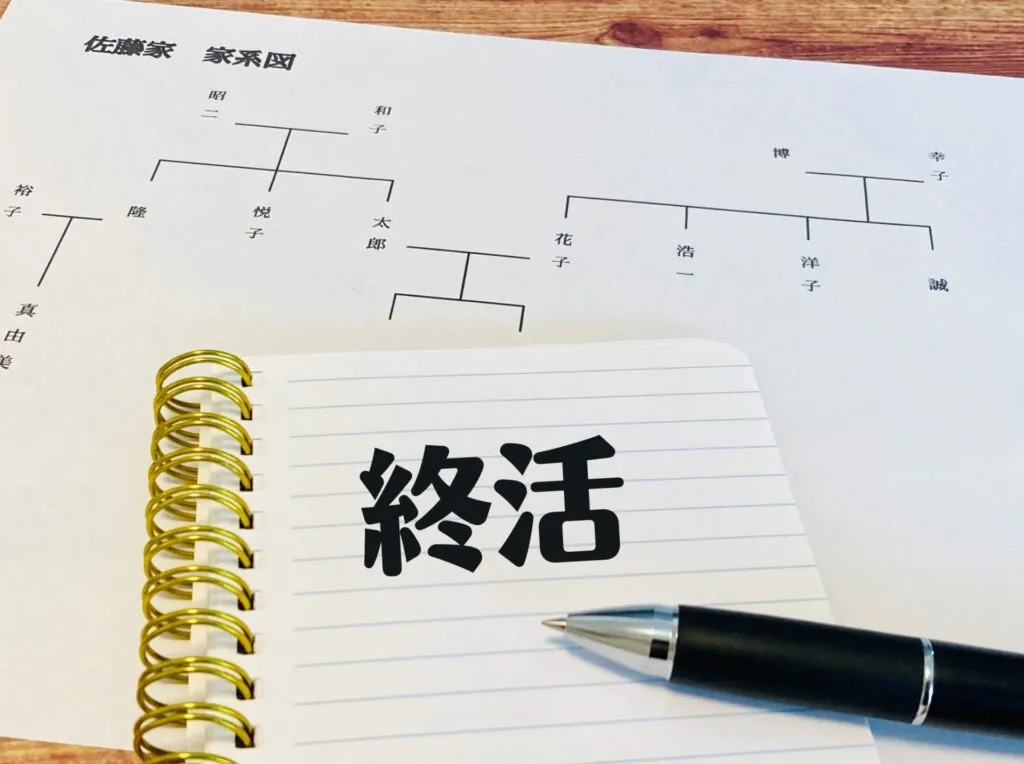 終活とは、「人生の終わりについて考え、残す活動」要するに、ご自身が亡くなった時の身の回りの生前整理、病気などで判断力を失った時のために医療・介護についての要望・希望などを残す作業です。終活で準備をおこなうことで、将来の不安が少なくなり、残りの人生を楽しく過ごせると同時に残していく人たちの負担を減らすこともできるのです。終活において大事なことは、自分の望む最期を迎えられるように、元気なうちから準備することなのです。きちんと要望を家族や周りの人に伝えられ、ポジティブに考えらえる時に活動することが大事。そして自分が過去残されたときに苦労したことや、困ったことを自分が残していきたくないという経験則からの気持ちも、形として現わせます。どこまで思い通りになるかは別としても、自分の要望を、参考にでも残しておくことが自分にとっても、遺される人にとってもプラスに働くでしょう。
終活とは、「人生の終わりについて考え、残す活動」要するに、ご自身が亡くなった時の身の回りの生前整理、病気などで判断力を失った時のために医療・介護についての要望・希望などを残す作業です。終活で準備をおこなうことで、将来の不安が少なくなり、残りの人生を楽しく過ごせると同時に残していく人たちの負担を減らすこともできるのです。終活において大事なことは、自分の望む最期を迎えられるように、元気なうちから準備することなのです。きちんと要望を家族や周りの人に伝えられ、ポジティブに考えらえる時に活動することが大事。そして自分が過去残されたときに苦労したことや、困ったことを自分が残していきたくないという経験則からの気持ちも、形として現わせます。どこまで思い通りになるかは別としても、自分の要望を、参考にでも残しておくことが自分にとっても、遺される人にとってもプラスに働くでしょう。終活を始めるタイミング

終活を始めるタイミング
・定年したとき・大きな病気をしたとき・近親者が亡くなったとき
終活の全体の流れ
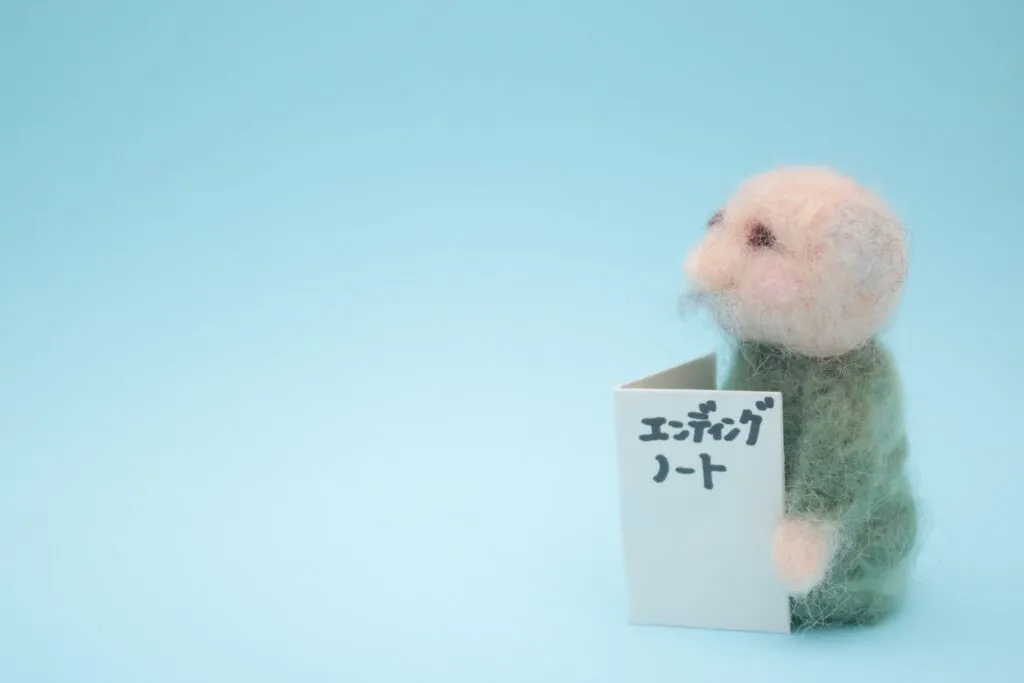
エンディングノートに記しておくこと
・エンディングノートを書くこと・お墓をどうするか決める事・葬式をどうするか決める事・不動産や資産をどうするか決める事・資産や貯金の暗証番号などを記載しておくこと・保険の棚卸しておくこと・不用品の処分
エンディングノートプラスして記しておくこと
・介護の施設の希望・看取り希望
終活ステップ1:エンディングノートを活用してみよう
エンディングノートとは、もしものときに備えて自分の人生の最期について希望を書いておく、重要項目を残しておくものです。要するに、終活した内容、結果を残していく人に伝えるものですね。エンディングノートに必要情報をまとめていれば、家族への負担が確実に減らせますし、自分の希望も叶えられます。エンディングノートは遺言書ではないため、法的な効力はありません。あくまでも、思いとして残すものです。エンディングノートは、ネットでも本屋さんなどでも簡単に手に入ります。自分で作成するのも良いですが、最近のエンディングノートは記すことを導いてくれていますので、かなり参考になりますよ。終活ステップ2:財産整理について
終活の中のこの「財産整理」は、一番気になるところではあると思います。お金のことは、近しい人であってもあまり知らないこともあり、本人しかわからないということも多いですからね。財産には、日常つかうような流動性のあるものや、貯金や資産などの収益性の高いものも存在します。特に預貯金などの場合は、契約ごとなので銀行の通帳や印鑑、カードの暗証番号などが必要になってきますし、それらがどこにあるかも伝えておく必要があります。現在、ネットバンキングなどもありますので、その場合の対処も書き記しておくことをお勧めします。あとは、保険です。保険も気づかないことが多いのです。受取人やその保険の仕組みなどを記しておきましょう。持っている不動産に関しては、名義の確認と書類がどこにあるかを記しておけば、OKです。もう一つ大変なのは、ローンです。ローンや借金が現時点である場合、その契約書や内容を記しておきましょう。住宅ローンなどの中には、契約者の死亡で払わなくてよくなるケースもあります。終活ステップ3:不用品処分、売却について
断捨離が必要な理由は、終活する時に遺族の負担を減らせるからです。自治体回収やリサイクルショップ、不用品回収業者などを利用することで、費用がかさばることはなくなります。身の回りの整理は、身体が動かなくなってからでは難しいので、元気なうちからやっておくと良いですよ。また、写真などデータでの保存しているものもあるかと思います。不要なデータは処分しておき、残しておきたいデータは、家族もわかる形で保存しておくことをお勧めします。終活ステップ4:人脈整理について
人脈に関しては、かなり個人的なことなので遺族たちが知り得ることは表面的なものだけです。葬儀に呼びたい人や訃報を伝えたい人がいる場合は、勤め先や電話番号・メールアドレスなどできるだけ記載しておくと、家族がスムーズに連絡できます。自分が病気になってお見舞いなど来て欲しい来て欲しくないという希望があれば、これも書いておくことが良いでしょう。終活ステップ5:お墓について
終活において、そして遺族のすることにおいてこのお墓問題は、現代の大きな課題であり大きな悩みになっていることです。お墓を承継するのかどうするのか?お墓に入れるようにすればそれで解決・・ではなくお墓がある以上管理をしていく必要があり、その管理をするのは遺族になるわけです。また、承継する家族がいない場合、改葬して新しいお墓を用意するのか墓じまいして永代供養のお墓をさがすのかなどということもあります。こういう遺族側や第三者側からし辛い話ほど、自分から元気なうちにしておくことが残していく人、自分のためになります。現代のお墓の一般的な相場はお墓の一般的な相場
・ 公営墓地費用の目安は年間1,000〜10,000円・民営墓地管理費用の目安は5,000〜15,000円・寺院墓地管理料は数千円〜数万円
終活ステップ6:葬儀について
昨今は、コロナもあってかなり簡素化した葬儀になっています。それを自分の時はどのような形にしたいかを記すことは、遺族にとっても負担を減らすことにもなりますし、本人の希望を叶えたいという遺族の気持ちを安心させてあげる事ができます。葬儀にかかる費用の相場は、飲食費や返礼品を合わせて200万円前後が相場です。葬儀の規模、喪主になってほしい人・頼みたいこと、宗派や宗教、菩提寺の連絡先、葬儀業者、使用してほしい遺影写真、参列者など自分の希望がある限り記しておきましょう。終活ステップ7:遺書の作成について
この遺書というものがあるとないとでは、状況によって大きく変わってきます。エンディングノートと違って、遺書は法律的に有効になるものもあるからです。主に自筆の遺言書と公正証書遺言があります。公正証書の場合は、公証人立ち会いのため、記入ミスによる無効の可能性を低くすることができます。結局ミスなどがあり条件を満たさなくなると、遺言書は無効になってしまいます。公正証書遺言は、費用が必要ですが遺言書を準備しておくことで、財産を自分の希望の人に渡せること、相続人の争いが起きないことなどのメリットがあります。遺言書の正式な種類は3つあります。この中で一般的なものは、自筆と公正証書ですが、後の事を考えると公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言遺言者が、自筆で氏名・日付・遺言内容全てを書き、署名、押印して作成する。添付する財産目録については、自書なくてもよいものとされるが、その場合は各頁に署名押印を要する。自ら保管しても良いですが、自筆証書遺言保管制度を利用して、遺言者本人によって遺言保管所に遺言書の保管を申請することもできます。公正証書遺言公証人および証人(2名以上)の前で遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が筆記、各人が署名、押印して作成。秘密証書遺言遺言者自身が遺言書を作成封印し、封印された遺言書の封紙に公証人および証人(2名以上)が署名、押印。終活ステップ8:終活その他の重要なこと
終活と言うと亡くなることを想定しているようですが、亡くなる時だけでなく認知症や要介護になったときのためにも役立ちます。認知症になると、財産管理の内容も伝えられない状態になりますので、家族や周囲がどのように対応したらよいか本人の意思がわかりません。それに、介護などの費用がかなりかかってきますが、その工面などをする場合にも記したものがなければ、自分たちで負担するだけになります。例えば、一人住んでいた自宅を売却するなどの手続きもできないのです。そこで、有効な方法として注目されているのが家族信託というのがあります。家族信託をしておけば家族が動けるので安心です。また、時代の高齢化により、長期介護や入院生活を送る高齢者が増えてきています。自分が倒れたときや認知症で判断能力を失ったとしても、家族が困らないように、必要な準備をしておくことが老後の安心に繋がります。終活マニュアルのまとめ