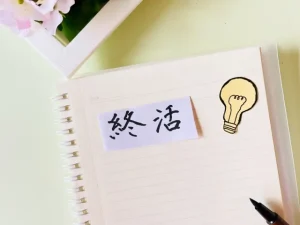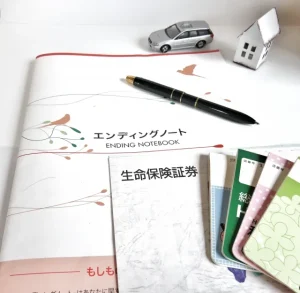人生の終わりに備え、身の回りの整理などを行う終活について、自ら調査したり、親族やパートナーと話し合った経験があるのではないでしょうか。
しかし、新型コロナウイルス感染症で死をより身近に連想してしまうことがあり、終活について、他人に気軽に相談や話しづらい雰囲気があります。
私たちは、生まれたときから、いつかは死ぬということが決まっています。
人生の終わりを迎え、そのことを考えたとき、一人では抱えられない悩みや問題があります。
例えば、自分や親族の健康、家族関係、葬儀、相続などがあります。
これらの問題は複雑に絡み合っており、簡単に解決できません。
そのような悩みに対し、終活カウンセラーは、一括してヒアリングし、問題を整理しながら、ご自身や親族の終活に対する根本原因や悩みがどこにあるのか一緒に探り、必要に応じて各専門家につなぎます。
終活カウンセラーは、超高齢社会となった日本で、あなたの身近にいる相談役です。
本書では「終活カウンセラー」についてその役割などを分かりやすく解説します。

目次
第1章:終活とは
ここでは、終活の目的やメリット、デメリットなどを紹介します。 終活を行う目的は人それぞれ異なります。 思い描く最期を迎えるための準備と考える人もいれば、自分らしい人生をまとめ上げるための活動と考える人もいます。 さらに、遺族や残される家族、子どものために終活を行う人もいます。 終活とは、人生のエンディングを達成するための活動や準備段階のことであり、残される家族への思いやりです。 死を考えることは縁起が悪いというのは昔の考え方です。 現在では、自分の死や死後について自ら考える必要があります。 生き方を自由に選択できるのと同様に、人は死に方も自由に選択できます。 また、健康な内に身の回りを整理し、残された家族の負担を軽減することだけでなく、自分の中を整理することで、残りの人生をより豊かに過ごす目的があります。 かつての日本では、家族がひとつ屋根の下に暮らし、さらに近所づきあいなど地域社会の結びつきが強かったため、死を前にしても疎外感や孤独感に襲われず、自分の死後のことを家族や地域社会に任せられるという意識を持つことができました。 終活が注目を集めることになった背景は、少子化と高齢化です。 家族と離れて一人で暮らす高齢者が増えた現在、周囲に迷惑をかけず自分が死んだ後の準備をしておく必要があります。 最近では、終活をテーマとして取り上げる記事やメディアが多くなり、終活セミナーなど終活に特化したイベントが開催されています。終活で得られるメリットとデメリットをまとめます。
メリット
自分の意向や意志を家族に伝えられる 残りの人生でやるべきことの優先順位が見える 家族や遺族の負担を軽減できる 相続トラブルを回避できるデメリット
自らの死を意識することで気分が落ち込む場合がある 残りの人生に精神的な負担となる第2章:終活カウンセラーとは
終活カウンセラーは、一般社団法人終活カウンセラー協会が認定する民間資格です。 相続、遺言、保険、葬儀、墓、介護などの終活に関する幅広い知識や人脈を持ち、相続人の希望や悩みをヒアリングし、具体的にどうすればいいのかをナビゲートします。 エンディングノート作成のアドバイスをはじめ、必要に応じて、弁護士や行政書士、税理士などの専門家や医療機関、介護施設、葬儀会社への橋渡しや、書類作成や申請の立ち合いも行います。 自身の終活のために資格を取得する人がいるほか、弁護士や税理士、葬儀関係者などの専門家が資格を取得していることもあります。 終活カウンセラーができることは、エンディングノート、遺言書作成のアドバイス、相続、保険、葬儀、介護の相談、専門家への仲介があります。 これまでの終活は、本、新聞記事、有料・無料セミナーで情報収集し、ノートなどにどのような生活スタイルを希望するのかが一般的ですが、現在では、オンライン上で記録に残すことで、家族や遺族が故人の遺志を確認しやすくなり、情報管理がしやすくなっています。